働き方が多様化し、副業・兼業が注目される中、法律関連の業務に携わる方でダブルワークに取り組む会社員も増えてきました。法務部員として培ってきた契約書作成・審査、法律相談、コンプライアンス体制構築といったスキルは、多くの企業にとって有用であり、副業市場においても一定の需要が見込めます。
ただし、「稼げる」かどうかは、個々のスキルレベル、弁護士資格の有無、そして何よりも積極的に案件を獲得するための行動力によって大きく左右されます。高単価の案件を獲得するためには、特定の専門分野における深い知識や、実績を示すポートフォリオなどが重要になります。
コンサル特化で高単価の案件多数/はじめての案件探しにもおすすめ
フリーコンサルタント.jp
業界最大級のコンサル案件/上流工程の求人に強いエージェント
コンサルデータバンク
副業案件が豊富/クライアントと直接契約が可能
この記事では、そんな法務関連の仕事を受注し、収入アップを実現するための方法について紹介します。業務委託案件の単価相場や求人情報の探し方、注意点についてみていきましょう。
法務で副業はできる?
法務の経験を活かして副業でお金を稼ぐことはできるのでしょうか。副業動向、対応可能な範囲、副業マッチングの仕組みについてみていきましょう。
副業を許可する会社は増えている
近年、働き方の多様化や個人のキャリア形成への意識の高まりを背景に、副業を認める企業が増加傾向にあります。かつては終身雇用制度が一般的であり、社員の囲い込みや情報漏洩のリスクを懸念して副業を禁止する企業が多数派でしたが、労働人口の減少や優秀な人材の確保といった観点から、柔軟な働き方を許容する動きが広がっています。
従業員にとっては、収入の増加だけでなく、本業で得られないスキルや経験の獲得、キャリアの選択肢の拡大といったメリットがあり、企業側も、従業員のモチベーション向上や新たな知識・視点の導入、人材流出の抑制といった効果を期待しています。
ただし、副業を許可する企業においても、情報漏洩や競業避止義務、本業への支障といった点には注意が必要であり、副業の種類や時間、内容について一定の制限を設けている場合がほとんどです。副業を検討する際には、自社の就業規則をしっかりと確認し、許可されている範囲内で活動を行う必要があります。また、副業を行うことで本業に支障が出ないよう、時間管理や体力管理を徹底することも求められます。企業と従業員双方にとって、副業がポジティブな影響をもたらすためには、適切なルール作りと相互理解が不可欠と言えるでしょう。
弁護士資格の有無で対応できる範囲が異なる
法律関連の業務においては、弁護士資格の有無が対応できる業務範囲に大きな影響を与えます。弁護士資格を持つ者は、法律相談、契約書作成・レビュー、訴訟・紛争解決、知的財産関連業務など、法律事務全般を取り扱うことが可能です。高度な専門知識と法的判断が求められる業務は、原則として弁護士資格を有する者のみが行うことができます。一方、弁護士資格を持たない法務経験者の場合、契約書作成・レビューの補助、法務調査、コンプライアンス関連業務のサポート、法務翻訳・校正、法務事務など、弁護士の指示の下に行える業務や、法律判断を伴わない周辺業務が中心となります。例えば、契約書のドラフト作成やレビューにおいても、最終的な法的判断や責任は弁護士が負うことになります。
また、顧客との直接的な法律相談や交渉代理は、非弁行為に該当する可能性があるため、行うことはできません。したがって、自身のスキルや経験、そして保有する資格に応じて、適切な副業案件を選択する必要があります。弁護士資格がない場合でも、これまでの法務経験で培った知識やスキルは十分に活かすことができ、企業や弁護士事務所にとって貴重な戦力となるでしょう。
非弁行為とは
非弁行為(ひべんこうい)とは、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関して法律事務を取り扱うことを業とすることです。これは弁護士法第72条で禁止されています。
副業マッチングの活用
近年、多様な働き方を支援するサービスとして、副業マッチングの仕組みが注目を集めています。法務部員の副業も例外ではなく、エージェントやクラウドソーシングのプラットフォームを活用することで、企業や個人が求める法務スキルと、法務経験を持つ個人のスキルを効率的に結びつけることが可能です。副業マッチングのサイトには、スポット案件から顧問契約のような継続的な案件まで、様々な種類の仕事が掲載されており、希望する働き方に合った案件を探しやすくなっています。また、自身のスキルや経験を登録しておくことで、企業側からスカウトを受ける可能性もあります。
プラットフォームによっては、契約締結や報酬の支払いなどを仲介してくれるため、安心して取引を進めることができます。ただし、サービスの利用規約や手数料、案件の信頼性などを十分に確認することが大切です。登録後はマッチングの仕組みを上手に活用することで、時間や場所に縛られない柔軟な働き方を実現し、自身の法務スキルを新たなフィールドで活かすことができるでしょう。
法務の副業案件の現状:スキルと単価相場
法務の副業で必要なスキルと報酬の単価相場についてみていきましょう。
業務委託の法務案件で求められるスキル
業務委託の法務案件において求められるスキルは、案件の内容や企業の規模、業種によって多岐にわたりますが、共通する要素がいくつか存在します。まず、契約法に関する深い知識は不可欠であり、多種多様な契約書の作成、レビュー、修正を的確に行う能力が求められます。企業の事業内容や取引形態を理解し、潜在的なリスクを洗い出し、適切な条項を盛り込むスキルは非常に重要です。次に、コンプライアンスに関する知識も重要度を増しており、企業が法令や規制を遵守するための体制構築や運用に関する支援、社内規程の作成や見直しなどが求められます。また、知的財産法に関する知識や、M&A、訴訟・紛争解決といった特定の専門分野に関するスキルは、高単価の案件につながる可能性が高いです。
さらに、法的な知識だけでなく、ビジネス感覚やコミュニケーション能力もあるとよいでしょう。企業の担当者や他の部門のメンバーと円滑に連携し、法的な観点からビジネス上の課題解決に貢献する姿勢が求められます。加えて、近年では、プライバシー保護やサイバーセキュリティに関する知識のニーズも高まっており、これらの分野に精通している人材は市場価値が高いと言えます。業務委託の法務案件では、即戦力として活躍できる経験と専門性が重視される傾向にあります。
法務案件で副業の単価相場
法務案件の副業における単価相場は、案件の種類、難易度、求められるスキル、契約形態、そして個人の経験や実績によって大きく変動します。スポット的な契約書レビューや法律相談の案件であれば、数千円から数万円程度が相場となることが多いです。一方、顧問法務のように継続的な関与が求められる案件や、M&A、知的財産関連などの専門性の高い案件では、月額数十万円以上の単価となることもあります。時間単価で契約する場合は、経験の浅い方であれば3,000円〜5,000円程度、高度な専門知識や豊富な経験を持つ方であれば10,000円以上となるケースも珍しくありません。
業務委託契約の場合、成果報酬型や固定報酬型など、契約形態によっても報酬体系は異なります。副業マッチングプラットフォームなどでは、様々な法務案件の単価が公開されているため、自身のスキルや経験と比較しながら相場感を把握することができます。ただし、提示されている単価はあくまで目安であり、個別の交渉によって変動する余地があることを理解しておく必要があります。
自身の市場価値を正確に把握し、適切な単価で副業に取り組むためには、これまでの実績やスキルを客観的に評価し、積極的に交渉することが重要です。また、複数のプラットフォームやエージェントを活用して情報収集を行うことも有効な手段と言えるでしょう。
法務部員の副業案件の種類
法務部員の副業で獲得できる案件の種類についてみていきましょう。
契約書関連業務
法務の副業案件の中でも特に多いのが、契約書に関連する業務です。企業活動において契約は不可欠であり、その種類も多岐にわたるため、外部の専門家の力を借りたいというニーズが常に存在します。具体的な業務としては、新規に締結する契約書の作成、既存の契約書のリスクレビューや修正、翻訳などが挙げられます。契約書の作成においては、企業の事業内容や取引内容を正確に理解し、将来起こりうるリスクを想定した上で、自社に有利かつ相手方にも納得してもらえるような条項を盛り込む能力が求められます。レビュー業務では、相手方が作成した契約書に潜むリスクを見抜き、修正案を提示したり、注意点を指摘したりする法的知識と経験が必要です。また、グローバル展開を進める企業においては、英文契約書の作成や翻訳のニーズも高まっています。これらの業務を遂行するためには、民法、商法といった基本的な法律知識に加え、契約の種類に応じた専門的な知識や、交渉力、コミュニケーション能力も重要となります。副業として契約書関連業務に取り組む際には、過去にどのような種類の契約書作成・レビュー経験があるのかを明確にし、自身の得意分野をアピールすることが案件獲得の鍵となります。
コーポレート関連業務
コーポレート関連業務は、企業の組織運営や活動全般に関わる法務業務であり、副業案件としても一定のニーズがあります。具体的には、株主総会や取締役会の運営に関するアドバイスや書類作成、組織再編(合併、分割など)に関する法務サポート、会社設立や解散に関する手続きの支援などが挙げられます。また、企業が資金調達を行う際の法務手続きや、知的財産権の管理・活用に関するアドバイスもコーポレート関連業務に含まれる場合があります。これらの業務は、会社法をはじめとする企業法務に関する深い知識が求められるのはもちろんのこと、企業の経営戦略や事業計画を理解し、法的な側面から適切なアドバイスを行う能力も重要となります。特にスタートアップや中小企業においては、社内に専門の法務担当者がいない場合が多く、外部の専門家に対して幅広いコーポレート関連業務のサポートを求める傾向があります。副業としてこれらの案件に取り組む際には、過去にどのような規模や業種の企業に対して、どのようなコーポレート関連業務の経験があるかを具体的に示すことが重要となります。
コンプライアンス関連業務
企業の持続的な成長と信頼確保のために不可欠なコンプライアンス(法令遵守)に関する業務も、法務の副業案件として注目されています。近年、企業を取り巻く法規制は複雑化しており、企業規模や業種を問わず、コンプライアンス体制の強化が求められています。具体的な業務としては、社内規程の作成・改訂、従業員向けのコンプライアンス研修の実施、内部通報制度の構築・運用支援、リスクアセスメントの実施、個人情報保護法や不正競争防止法などの関連法規に関するアドバイスなどが挙げられます。これらの業務を遂行するためには、関連法規の知識はもちろんのこと、企業の事業内容や組織文化を理解し、実効性のあるコンプライアンス体制を構築・運用する能力が求められます。また、従業員に対して分かりやすく説明するコミュニケーション能力や、潜在的なリスクを早期に発見し対応する問題解決能力も重要となります。副業としてコンプライアンス関連業務に取り組む際には、どのような業種や規模の企業で、どのようなコンプライアンス体制の構築・運用に携わった経験があるかを具体的にアピールすることが有効です。
プライバシー関連業務
デジタル化の進展に伴い、個人情報の取り扱いに関する法規制が世界的に強化されており、プライバシー関連業務のニーズが急速に高まっています。日本においては個人情報保護法、海外においてはGDPR(EU一般データ保護規則)など、企業が遵守すべき法規制は多岐にわたります。具体的な副業案件としては、プライバシーポリシーや利用規約の作成・改訂、個人データの取得・利用・保管に関するアドバイス、データ侵害発生時の対応支援、従業員向けのプライバシー研修の実施などが挙げられます。これらの業務を遂行するためには、関連法規の深い知識はもちろんのこと、企業の事業内容やデータフローを正確に理解し、リスクを評価した上で適切な対策を講じる能力が求められます。また、国際的なデータ移転に関する知識や、最新の法規制動向を把握していることも重要となります。副業としてプライバシー関連業務に取り組む際には、どのような種類の個人情報を取り扱った経験があるか、どのような法規制に対応した経験があるかを具体的に示すことが、案件獲得において有利に働きます。
法務周辺業務
法務の専門知識を直接的に活用する業務以外にも、法務経験や知識を活かせる周辺業務も副業の選択肢として存在します。例えば、契約書や法律関連文書の翻訳・校正、法律や判例に関する調査・分析、法務関連のセミナーや研修資料の作成補助、法務部門の業務効率化に関するコンサルティングなどが挙げられます。これらの業務は、高度な法律知識が必須ではない場合もありますが、法的な素養や論理的な思考力、正確な情報収集能力などが求められます。また、法務部門における実務経験がある方は、書類整理やデータベース管理、契約管理システムの導入支援といった業務で貢献できる可能性もあります。これらの周辺業務は、時間や場所に比較的柔軟に対応できる案件も多く、法務の知識を活かしつつ、自身のライフスタイルに合わせた働き方を実現しやすいというメリットがあります。副業としてこれらの案件に取り組む際には、これまでの法務経験の中でどのような周辺業務に携わってきたか、どのようなスキルを活かせるかを具体的にアピールすることが重要となります。
法務担当者の副業案件の探し方
企業法務を担当する副業で案件を探す方法についてみていきましょう。
エージェント
法務の専門知識や経験を生かした副業案件を探す上で、業務委託の求人を扱う専門エージェントを活用することは有効な手段の一つです。エージェントは、企業の人手不足や専門性の高い業務ニーズを把握しており、個人のスキルや希望条件に合致する案件を紹介してくれます。多くの場合、非公開の案件情報も扱っているため、自力では見つけにくい魅力的な案件に出会える可能性があります。
また、エージェントによっては、契約条件の交渉や事務手続きのサポートも提供してくれるため、安心して副業に取り組むことができます。ただし、エージェントの利用には手数料が発生する場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。複数のエージェントに登録し、比較検討することで、より自分に合った案件を見つけやすくなるでしょう。
クラウドソーシング
近年、多様な働き方が広がる中で、クラウドソーシングプラットフォームも法務の副業案件を探すための有力な選択肢となっています。これらのプラットフォームには、契約書作成やレビュー、法律相談、知的財産関連業務など、幅広い種類の法務関連案件が掲載されています。時間や場所にとらわれずに仕事ができる案件も多く、自分のライフスタイルに合わせて柔軟に働くことが可能です。一方で、報酬額や契約条件は案件によって大きく異なるため、内容をしっかりと確認する必要があります。
また、多くの応募者の中から選ばれるためには、自身のスキルや経験を具体的にアピールする工夫が求められます。積極的に提案を行い、実績を積み重ねることで、より高単価な案件を獲得するチャンスも広がります。
同僚や知人からの紹介
これまでのキャリアで築いてきた人脈は、法務の副業案件を探す上で非常に貴重な財産となります。以前の職場の同僚や上司、あるいは大学時代の友人など、様々なつながりを通じて、企業や個人が抱える法務関連のニーズを紹介してもらえることがあります。直接的な紹介であるため、案件の詳細や背景事情を事前に把握しやすく、信頼関係に基づいたスムーズな連携が期待できます。
また、紹介者の信用によって、比較的良い条件で仕事を受けられる可能性もあります。日頃から周囲との良好なコミュニケーションを心がけ、自身のスキルや副業への意欲を伝えておくことが重要です。積極的に情報交換を行うことで、思わぬチャンスに繋がるかもしれません。
直接営業
自らの専門性や強みを明確に理解している場合、企業や個人に対して直接営業を行うことも副業案件獲得の有効な手段です。ターゲットとする企業や個人を選定し、自身のスキルがどのように貢献できるかを具体的に提案することで、新たな仕事の機会を創出できます。例えば、特定の業界に精通している場合は、その業界の企業に対して法務顧問や契約書作成支援などを提案することができます。直接営業は、自身の裁量で活動範囲や条件を決められるメリットがある一方、案件獲得までの時間や労力がかかるという側面もあります。
自身のウェブサイトやSNSなどを活用して情報発信を行い、実績や専門性をアピールすることも効果的です。根気強く活動を続けることで、長期的な信頼関係を築き、継続的な案件獲得に繋がる可能性があります。
法務の副業におすすめのエージェント
法務の副業探しにおすすめのエージェントを紹介します。
Strategy Consultant Bank
『Strategy Consultant Bank![]() 』は、コンサルタント向けの案件紹介エージェントとして、高単価案件を豊富に扱っている点が特徴です。法務の専門知識や経験を持つ方が、これまでのスキルを生かして副業に取り組む上で、高収入を得られる可能性のある案件が見つかるかもしれません。上場企業や外資系企業の案件も多く、より専門性の高い業務に携わるチャンスも期待できます。リモートワークが可能な案件も多数掲載されているため、時間や場所にとらわれずに柔軟な働き方を希望する方にとって、選択肢の一つとなるでしょう。自身のスキルや経験を登録し、エージェントに相談することで、条件に合った法務関連の仕事を紹介してもらえる可能性があります。
』は、コンサルタント向けの案件紹介エージェントとして、高単価案件を豊富に扱っている点が特徴です。法務の専門知識や経験を持つ方が、これまでのスキルを生かして副業に取り組む上で、高収入を得られる可能性のある案件が見つかるかもしれません。上場企業や外資系企業の案件も多く、より専門性の高い業務に携わるチャンスも期待できます。リモートワークが可能な案件も多数掲載されているため、時間や場所にとらわれずに柔軟な働き方を希望する方にとって、選択肢の一つとなるでしょう。自身のスキルや経験を登録し、エージェントに相談することで、条件に合った法務関連の仕事を紹介してもらえる可能性があります。
フリーコンサルタント.jp
『フリーコンサルタント.jp![]() 』は、様々な分野のコンサルタント案件を取り扱っており、法務関連の副業案件が見つかる可能性もあります。企業の経営課題に対する知見が求められるコンサルティング案件が中心ですが、法務の専門知識を活かせるアドバイザリー業務などの案件も探してみる価値はあるでしょう。サイト上で、週数日や短時間稼働の案件も掲載されていることがあるため、本業を持ちながら副業として法務の知識を提供したいと考える方にとって、働きやすい案件を見つけられる可能性があります。自身のスキルや経験を登録し、興味のある案件に積極的に応募することで、副業の機会を広げることができるでしょう。
』は、様々な分野のコンサルタント案件を取り扱っており、法務関連の副業案件が見つかる可能性もあります。企業の経営課題に対する知見が求められるコンサルティング案件が中心ですが、法務の専門知識を活かせるアドバイザリー業務などの案件も探してみる価値はあるでしょう。サイト上で、週数日や短時間稼働の案件も掲載されていることがあるため、本業を持ちながら副業として法務の知識を提供したいと考える方にとって、働きやすい案件を見つけられる可能性があります。自身のスキルや経験を登録し、興味のある案件に積極的に応募することで、副業の機会を広げることができるでしょう。
コンサルデータバンク
『コンサルデータバンク![]() 』は、企業とコンサルタントが直接繋がることができるプラットフォームであり、仲介手数料がかからない点が特徴です。法務の専門家として登録することで、企業から直接スカウトを受けたり、掲載されている法務関連の案件に応募したりすることができます。スポットコンサルティングのような短時間の案件も扱っているため、まずは、小規模から副業を始めたいと考える方にも適しています。自身のスキルや経験を詳細に登録し、積極的に情報発信を行うことで、企業とのマッチングの機会を増やすことができるでしょう。直接企業と交渉することで、自身の希望する条件に近い形で副業を進められる可能性があります。
』は、企業とコンサルタントが直接繋がることができるプラットフォームであり、仲介手数料がかからない点が特徴です。法務の専門家として登録することで、企業から直接スカウトを受けたり、掲載されている法務関連の案件に応募したりすることができます。スポットコンサルティングのような短時間の案件も扱っているため、まずは、小規模から副業を始めたいと考える方にも適しています。自身のスキルや経験を詳細に登録し、積極的に情報発信を行うことで、企業とのマッチングの機会を増やすことができるでしょう。直接企業と交渉することで、自身の希望する条件に近い形で副業を進められる可能性があります。
法務の副業でエージェントを利用する場合、『Strategy Consultant Bank![]() 』、『フリーコンサルタント.jp
』、『フリーコンサルタント.jp![]() 』、『コンサルデータバンク
』、『コンサルデータバンク![]() 』などがおすすめです。それぞれのエージェントは、特徴や強みが異なるため、自分のスキルや希望条件に合わせて相性の良いサービスを選びましょう。複数のエージェントに登録することで、より多くの案件情報を得ることができます。
』などがおすすめです。それぞれのエージェントは、特徴や強みが異なるため、自分のスキルや希望条件に合わせて相性の良いサービスを選びましょう。複数のエージェントに登録することで、より多くの案件情報を得ることができます。
法務の副業求人を探す際のポイント
法務の副業で求人情報を探す際のポイントについて紹介します。
週1〜2日などで対応可能か
法務の副業求人を探す上で、まず確認すべき重要なポイントは、自身の本業との兼ね合いを考慮し、無理なく対応できる勤務日数や時間であるかどうかです。多くの副業希望者は、本業を持ちながら限られた時間の中で副収入を得たいと考えているため、週に1〜2日程度の稼働で対応可能な案件を探すことが現実的です。求人情報には、具体的な勤務日数や時間帯が明記されていない場合もあるため、応募前にしっかりと確認することが不可欠です。もし記載がない場合は、面談や問い合わせの際に、自身の希望する働き方を具体的に伝え、企業側のニーズとの調整が可能かどうかを確認しましょう。柔軟な働き方を認めている企業であれば、副業という形でも法務の専門知識や経験を十分に活かすことができるはずです。
平日夜、早朝、土日で稼働できるか
本業への影響を最小限に抑えながら副業に取り組むためには、平日の夜間や早朝、あるいは土日といった、本業以外の時間を有効活用できる案件を選ぶことが重要になります。法務の業務内容は多岐にわたりますが、契約書作成やレビュー、法律相談など、時間や場所に比較的制約を受けにくい業務であれば、これらの時間帯での対応が可能な場合があります。求人情報に記載されている勤務時間や業務内容を確認し、自身のライフスタイルに合わせて無理なく対応できるかどうかを検討しましょう。もし、具体的な記載がない場合は、応募先企業に自身の稼働可能な時間帯を伝え、業務遂行に支障がないかを確認することが大切です。柔軟な働き方を認めてくれる企業であれば、副業でも自身のスキルを十分に発揮できるでしょう。
フルリモート・在宅ワークで作業できるか
時間的な制約と同様に、場所の制約も副業選びにおいて重要な要素となります。特に、本業を持つ方が副業に取り組む場合、通勤時間を削減し、自宅などの好きな場所で作業できるフルリモートや在宅ワークの案件は大きな魅力となります。法務関連の業務の中には、資料作成やリサーチ、契約書のレビューなど、オンライン環境があれば場所を選ばずに遂行できるものが多く存在します。求人情報を確認する際には、「リモート可」「在宅ワーク可」といった記載があるかどうかをチェックし、もし記載がない場合は、応募先企業にリモートワークの可否について確認することが重要です。フルリモートや在宅ワークが可能な案件であれば、全国どこからでも応募できるため、より多くの選択肢の中から自分に合った副業を見つけやすくなります。
本業と競合しないか
副業を始めるにあたっては、自身の本業との競合関係が生じないかどうかを慎重に確認する必要があります。本業の就業規則で副業が禁止されている場合や、同業他社での副業が制限されているケースがあります。また、副業の内容が本業の業務と類似している場合、情報漏洩や利益相反のリスクが生じる可能性も否定できません。求人に応募する前に、自身の本業の就業規則を改めて確認し、副業が許可されているかどうか、また競業避止義務に関する規定がないかどうかを確認することが重要です。面接や契約締結の際には、副業の内容を具体的に伝え、本業との競合の可能性について企業側の見解を確認することも大切です。安心して副業に取り組むためには、事前にしっかりと確認し、トラブルを未然に防ぐことが不可欠です。
法務経験を活かした副業の始め方
法律業務の実務者として経験をつみ、副業を始める手順についてみていきましょう。
就職して実務経験を積む
法務の副業を始めるにあたって、まず何よりも重要なのは、企業の法務部門や法律事務所などに新卒採用や中途採用で就職して実務経験をしっかりと積むことです。契約書の作成・審査、法令調査、訴訟・紛争対応、コンプライアンス体制の構築・運用など、幅広い業務に携わることで、専門知識と実践的なスキルが磨かれます。これらの経験は、副業として法務サービスを提供する際の信頼性を高めるだけでなく、質の高い業務遂行の基盤となります。また、実務経験を通じて、自身の得意分野や興味のある領域を見つけることができるでしょう。
副業でどのような法務サービスを提供したいのか、具体的な方向性を定めるためにも、多様な業務経験は非常に有益です。最低でも数年間は企業法務や法律事務所での勤務経験を積み、法務担当者としての基礎力と応用力をしっかりと身につけることが、副業成功への第一歩と言えるでしょう。
スキルシートやポートフォリオを準備する
副業を始める準備段階として、自身のスキルや経験を具体的に示すスキルシートとポートフォリオの作成が不可欠です。スキルシートには、これまでの職務経歴、担当した業務内容、得意な法律分野、保有資格などを詳細に記載します。単に業務内容を羅列するのではなく、どのような成果を上げたのか、どのような貢献ができたのかを具体的に記述することで、自身の能力を効果的にアピールできます。ポートフォリオは、過去に作成・審査に関わった契約書、意見書、法務関連の資料などを匿名化して提示することで、実務能力を具体的に示すことができます。
もし公開できるものが少ない場合は、秘密保持契約に抵触しない範囲で、業務で得た知識や経験に基づいて作成した模擬的な資料などを加えることも有効です。これらの準備を通じて、自身の強みを明確化し、副業先に対して具体的なアピール材料を提供できるようになります。
副業先の案件を探す
スキルシートとポートフォリオが完成したら、いよいよ副業先の案件を探し始めます。法務の副業案件は、クラウドソーシングサイト、副業マッチングプラットフォーム、人材紹介サービスなど、様々な場所で見つけることができます。これらのプラットフォームでは、企業や個人が法務関連の業務を外部に委託する案件を掲載しており、自身のスキルや経験、希望する条件に合った案件を探すことが可能です。また、これまでの職務経験で築いた人脈を活用することも有効な手段です。同僚や取引先などに副業を検討していることを伝え、紹介や協業の機会を探るのも良いでしょう。
案件に応募する際には、自身のスキルシートやポートフォリオを提示し、これまでの経験や実績を具体的にアピールすることが重要です。報酬や契約条件などをしっかりと確認し、納得のいく条件で業務を開始できるように交渉しましょう。初めのうちは実績作りのために、比較的小さな案件から挑戦してみるのも良いかもしれません。
法務部員の副業で役立つ資格
法務部員の副業で役立つ資格について紹介します。
弁護士
法務部員の副業において、弁護士資格は非常に強力な武器となります。訴訟代理、法律相談、契約書作成・審査など、独占業務を含む幅広い法務サービスを提供できるため、高単価の案件を獲得しやすいでしょう。企業内での実務経験に加え、弁護士としての専門知識と倫理観は、クライアントからの信頼を得る上で大きなアドバンテージとなります。ただし、弁護士資格を取得するには難易度の高い試験に合格する必要があり、時間と労力を要します。また、副業を行う際には、所属する弁護士会への登録や、兼業に関する規定の確認が必要となる場合があります。資格取得のハードルは高いものの、その後の副業の可能性を大きく広げる資格と言えるでしょう。
弁理士
知的財産権に関する専門家である弁理士資格は、法務部員の副業においても大いに役立ちます。特許、商標、意匠などの出願代理や鑑定、知的財産に関するコンサルティングなど、専門性の高い業務を提供できます。特に、技術系の知識や経験を持つ法務部員であれば、その専門性を活かして活躍できるでしょう。近年、企業の知的財産戦略の重要性が高まっているため、弁理士のニーズは増加傾向にあります。弁理士資格を持つことで、企業内での業務経験に加えて、知的財産という専門分野での副業収入を得る道が開かれます。資格取得には専門的な知識が求められますが、差別化されたスキルとして副業市場で高い価値を発揮するでしょう。
行政書士
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続きの代理、権利義務・事実証明に関する書類の作成などを主な業務とする資格です。法務部員としての経験があれば、契約書作成や各種法規制に関する知識を活かし、許認可申請、会社設立、遺言書作成などの業務で副業を行うことができます。弁護士や司法書士と比較すると、独占業務の範囲は狭いものの、中小企業や個人からの依頼が多く、比較的取り組みやすい案件が多いのが特徴です。法務部での実務経験を活かしつつ、地域に根差した副業を展開したいと考える方にとって、行政書士資格は有効な選択肢となるでしょう。
司法書士
司法書士は、不動産登記、商業登記、供託手続き、裁判所や検察庁に提出する書類の作成、成年後見などの業務を行う資格です。法務部員として契約書や組織再編に関わる経験があれば、登記関連の知識を活かして副業に取り組むことができます。特に、不動産取引や会社設立などの際には、司法書士の専門知識が不可欠となるため、一定のニーズが見込めます。また、近年では高齢化に伴い、成年後見業務の需要も増加しています。司法書士資格を取得することで、登記業務を中心に、法務部での経験を活かした専門的な副業を展開することが可能になります。
法務の副業を始める際の注意点
法務の副業を始める際の注意点について解説します。
就業規則を確認し副業の許可を取る
法務の副業を検討する上で、必要なステップの一つが、現在勤務している会社の就業規則をしっかりと確認し、副業に関する規定を把握することです。多くの企業では、従業員の副業に関して何らかのルールを定めており、中には原則として禁止している場合や、事前の申請と許可を義務付けている場合があります。許可を得ずに副業を始めてしまうと、最悪の場合、懲戒処分の対象となる可能性もあります。そのため、副業を始める前に必ず就業規則を確認し、副業が許可されているかどうか、許可が必要な場合はどのような手続きを踏むべきかを確認しましょう。不明な点があれば、人事部や法務部に直接問い合わせることが重要です。円滑に副業を始めるためには、会社との良好な関係を維持し、ルールを遵守することが不可欠です。
確定申告を忘れないようにする
副業によって収入を得た場合、その所得に対しては原則として確定申告を行う必要があります。副業による所得が一定額を超える場合や、給与所得以外の所得がある場合は、自身で所得を計算し、税務署に申告・納税する義務が生じます。確定申告を怠ると、加算税や延滞税が課せられる可能性があり、法的なトラブルに繋がることもあります。副業を始める際には、どのような所得が確定申告の対象となるのか、必要な書類や手続きは何かを事前に理解しておくことが大切です。会計ソフトを活用したり、税理士に相談したりするなど、適切な準備と管理を行い、期限内に正確な確定申告を済ませるように心がけましょう。
本業とのバランスに注意する
副業を始める際には、本業とのバランスを十分に考慮することが非常に重要です。副業に時間を費やしすぎると、本業に支障が出たり、疲労が蓄積して体調を崩したりする可能性があります。法務の仕事は、責任が重く、集中力や正確性が求められるため、本業がおろそかになることは避けなければなりません。副業の量やスケジュールを慎重に検討し、無理のない範囲で活動することが大切です。また、副業の内容が本業の競合となる場合や、会社の信用を損なうような行為は厳に慎むべきです。常に本業を優先し、副業はあくまで余暇時間や休日を利用して行うという意識を持つことが、長期的に副業と本業を両立させるための鍵となります。
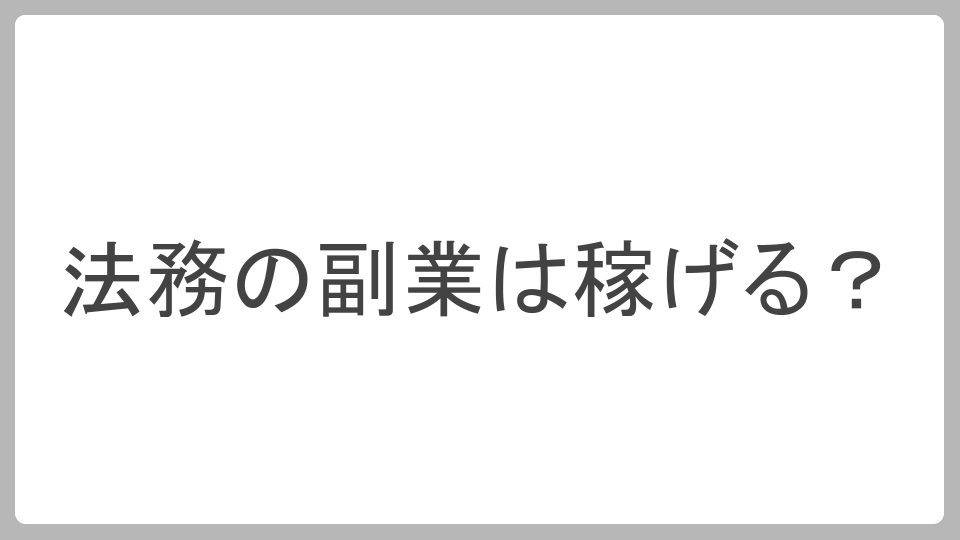
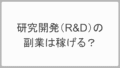
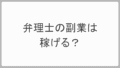
コメント